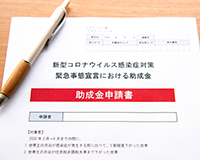フリーランスに消費税の納税義務はある?インボイス制度の対応も解説

インボイス制度の導入により、フリーランスも消費税に対する適切な対応が求められるようになりました。消費税の納税義務が発生する条件や、クライアントへの消費税請求のルールを正しく理解することが重要です。
本記事では、フリーランスが知っておくべき消費税の基本、インボイス制度導入に伴って適格請求書発行事業者となった場合の計算方法や請求書の書き方などについて解説します。
フリーランスが消費税を納める必要がある場合とは?
フリーランスとして活動する場合、すべての人に消費税の納税義務があるわけではありません。フリーランスが消費税を納めなければいけないかどうかは、フリーランスの売上高や事業形態によって異なります。以下、消費税の納税義務が発生する場合について説明します。
2年前の課税売上高が1,000万円を超えた場合
フリーランスが消費税の納税義務を負うかどうかは、2年前(基準期間)の課税売上高によって判断されます。
課税売上高が1,000万円を超えた場合、2年後の課税期間から消費税の納税義務が発生します。2年前の売上高が1,000万円以下であれば、免税事業者となり、消費税の納税義務は発生しません。
2年前の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合
2年前の課税売上高が1,000万円以下であっても、1年前の1月1日から6月30日まで(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合は、その翌年から課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。
「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合
消費税課税事業者選択届出書は、免税事業者がみずからの意思で課税事業者になるために税務署に提出する書類です。課税事業者になると、仕入税額控除が適用されたり、支払った消費税が多い場合に還付を受けられたりするメリットがあります。さらに適格請求書(インボイス)を発行できるようになり、クライアント(取引先)からの要請に応えられるのも利点です。
なお、2029年9月30日までの期間中は、適格請求書発行事業者の登録申請時に「消費税課税事業者選択届出書」の提出が不要となる経過措置があります。
適格請求書発行事業者として登録した場合
適格請求書発行事業者として登録すると、消費税を納める義務が発生します。2023年10月からインボイス制度が始まり、売上高が1,000万円以下のフリーランスでも「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して、課税事業者になるケースが増えています。
適格請求書発行事業者の登録を受けると、その後基準期間の課税売上高が1,000万円以下になっても免税事業者には戻れず、消費税の申告義務が継続します。
フリーランスはクライアントの請求書や見積書に消費税を含めてもいいのか?
一方、フリーランスはクライアントに対して消費税を請求できるのでしょうか。以下で、詳しく説明します。
フリーランスはクライアントに消費税を請求できる
フリーランスは、クライアントに対して消費税を含めた請求をすることができます。課税事業者であれば、報酬とは別に消費税を請求するのが一般的ですが、売上が1,000万円未満の免税事業者であっても、消費税を含めた請求は可能です。これは、売上が1,000万円に達していない免税事業者の場合でも同様です。
消費税を請求する際は、報酬額を確認する際に「報酬金額」と「消費税額」を明確に分けて考える習慣をつけることが大切です。また、クライアントとの間で消費税の取り扱いについて事前に確認し、合意を得ておくことで、後から発生するトラブルを防ぐことができます。
免税事業者でも消費税を請求できる理由
免税事業者が消費税を請求できるのは、消費税法第4条で「国内において事業者が行つた資産の譲渡等及び特定仕入れには、この法律により、消費税を課する」と定められているためです。法律上、免税事業者が消費税を請求してはいけないという規定はなく、請求自体は認められています。
消費税は間接税であり、最終的には消費者が負担する税金です。フリーランスも業務上の経費に消費税を支払っているため、消費税を請求しないと実質的な値引きとなり、利益が減少します。また、消費税は間接税であり、最終的な負担者は消費者です。そのため、請求自体に問題はありません。
課税事業者と免税事業者での違い
フリーランスが消費税を請求する際は、自身が課税事業者か免税事業者かによって扱いが違います。
・課税事業者の場合
支払った消費税を仕入税額控除できるため、消費税を請求することで支払った消費税分を回収可能です。
・免税事業者の場合
支払った消費税を仕入税額控除できませんが、納税義務がないため、消費税を請求しても国に納める必要はありません。
免税事業者であっても、クライアントに消費税を請求することは可能です。しかし、2023年10月に導入されたインボイス制度の影響により、適格請求書(インボイス)を発行できない免税事業者との取引を避ける企業も増えているため、免税事業者の場合、消費税を請求するかどうかは、取引先との関係や市場価格を考慮して判断しましょう。
免税事業者が消費税を請求する際の注意点
免税事業者が請求書を作成する際は、記載方法に注意が必要です。特に、「消費税」という表記を使用すると、取引先が課税事業者と誤解する可能性があるため、「税込」と記載するなどの配慮をすることが望ましいでしょう。
また、免税事業者は適格請求書(インボイス)を発行できないため、取引先が仕入税額控除を受けられない点も理解しておく必要があります。そのため、請求書には「この請求書は適格請求書ではありません」などの補足を加えるなど、取引先に対して誤解を招かないよう注意することが必要です。
インボイス制度導入でフリーランスが対応を迫られることとは?
2023年10月に導入されたインボイス制度は、フリーランスの消費税の取り扱いに大きな影響を与えています。これまで免税事業者として活動していたフリーランスは、どのような対応が迫られているのでしょうか。
適格請求書発行事業者の登録検討
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために、取引先が「適格請求書(インボイス)」の発行を求めるケースが増えています。そのため、フリーランスは免税事業者のままでいるのか、適格請求書発行事業者として登録するのかを判断しなければなりません。
・免税事業者
免税事業者とは、消費税の納税義務を免除されている事業者です。基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者が該当し、消費税の申告や納付が不要です。
・適格請求書発行事業者
適格請求書発行事業者は、インボイス制度において適格請求書(インボイス)を発行できる事業者です。課税事業者であることが条件で、税務署長に登録申請書を提出し、審査を経て登録します。クライアントが仕入税額控除を受けるために必要とする書類を発行できるのが、免税事業者と適格請求書発行事業者の大きな違いです。
適格請求書発行事業者として登録する場合、これまで免税事業者だったフリーランスも自動的に課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。そのため、単に登録するだけでなく、消費税の計算や納付を考慮した資金管理も必要になります。
免税事業者のままでいる場合
インボイス制度導入後も、免税事業者のままでいることは可能です。免税事業者のままでいるメリットは、消費税の納税義務がないため事務負担が少なくなることです。消費税の申告・納付が不要で、経理業務を簡素化できるため、特に会計処理の負担を抑えたい人にとっては適切な選択肢となります。また、すでに述べたように、免税事業者でもクライアントに消費税を請求はできます。
一方で、適格請求書(インボイス)を発行できないため、クライアント側は仕入税額控除を受けることができません。そのためクライアントが適格請求書発行事業者との取引を優先していることがあり、免税事業者のままだと、仕事をもらえない可能性があることに注意が必要です。
適格請求書発行事業者として登録する場合
適格請求書発行事業者として登録すると、引き続き取引先に適格請求書を発行できるため、仕入税額控除を受けたい企業クライアントとの取引を続けやすくなります。しかし、これまで免税事業者だったフリーランスにとって、消費税の納税義務が生じることは大きな変化です。消費税の申告・納付が必要となり、事務負担が増加することを考慮しなければなりません。
また、消費税を納める分だけ手取り収入が減る点にも、注意が必要です。特に、現在の報酬額が据え置きの場合、消費税分を支払うことで実質的な負担が増える可能性があります。登録を検討する際は、クライアントとの契約内容や収益への影響をよく考えた上で判断することが重要です。
適格請求書発行事業者となったフリーランスが知っておくべき消費税の計算方法
フリーランスが適格請求書発行事業者になると、消費税の計算方法は主に3つの選択肢があります。以下で、それぞれの計算方法を解説します。
1. 原則課税方式(本則課税)
原則課税方式は、最も基本的な消費税の計算方法です。消費税額は、課税売上げに係る消費税額から仕入・経費にかかった消費税額を差し引いて算出します。この方式では、すべての取引を正確に記録し、仕入税額控除を行うためインボイスの保存が必要となります。
計算式は次のとおりです。
<原則課税の計算式>
納税する消費税額=課税売上げに係る消費税額-仕入・経費にかかった消費税額
仕入れや経費が多い場合、納税額を抑えられる可能性がありますが、計算が複雑になるため、会計処理に慣れていないと手間が増える点に注意が必要です。
2. 簡易課税方式
簡易課税方式は、中小事業者の事務負担を軽減するために設けられた制度です。簡易課税方式では、課税売上高に係る消費税額にみなし仕入率を適用して仕入税額を推定します。簡易課税方式を選択できるのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者のみです。
計算式は次のとおりです。
<簡易課税の計算式>
納税する消費税額=課税売上高に係る消費税額-(課税売上高に係る消費税額×みなし仕入率)
みなし仕入率は業種によって異なり、40%から90%の範囲で設定されています。実際の仕入額が少ない事業者にとっては有利な場合があります。フリーランスエンジニアの場合は、サービス業なので、第5種事業の50%です。
■簡易課税制度の事業区分
| 事業区分 | みなし仕入率 |
|---|---|
| 第1種事業(卸売業) | 90% |
| 第2種事業(小売業・農業・林業・漁業) | 80% |
| 第3種事業(鉱業・建設業・製造業・電気業・ガス業・熱供給業・水道業) | 70% |
| 第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) | 60% |
| 第5種事業(運輸通信業・金融・保険業・サービス業) | 50% |
| 第6種事業(不動産業) | 40% |
参考元:国税庁「No.6509 簡易課税制度の事業区分」
適用には、課税期間が始まる日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を管轄の税務署に提出する必要があります。
3. 2割特例
2割特例は、インボイス制度導入に伴い、新たに課税事業者となった小規模事業者向けの特例措置です。2026年までの期間限定で、簡単な計算で納税額を求めることができます。
計算式は次のとおりです。
<2割特例の計算式>
納税する消費税額=課税売上高に係る消費税額-(課税売上高に係る消費税額×80%)
この方法では、売上にかかる消費税の2割のみを納税すればよいため、事務負担が大幅に軽減されます。適用期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの3年間で、事前の届出は不要です。
適用条件として、基準期間・特定期間の課税売上高等がともに1,000万円以下であることに加え、インボイス制度に登録して初めて消費税の納税義務が生じる事業者であることが必要です。個人事業主の場合、2割特例が利用できるのは2023年分の申告から2026年分の申告までとなります。
適格請求書(インボイス)の書き方
最後に、適格請求書発行事業者となったフリーランスが請求書の書き方について説明します。適格請求書(インボイス)には、以下の項目を必ず記載しなければなりません。
<適格請求書(インボイス)に記載しなければならない項目>
1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
2. 取引年月日
3. 取引内容(軽減税率対象品目の場合はその旨)
4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
5. 税率ごとに区分した消費税額等
6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
加えて請求書には、税込金額、本体価格(税抜価格)、消費税額の3つを明記することが基本です。消費税の表示方法は内税・外税どちらでも問題ありませんが、最終的な請求金額は必ず税込で表示しなければなりません。請求金額を税込で表示することで、取引先が支払うべき金額を明確に把握できます。
適格請求書(インボイス)を作成する際には、以下の点に注意が必要です。
登録番号の記載
適格請求書発行事業者は、登録番号の記載が必要です。例えば、「登録番号:T1234567890123」のように記載します。
内訳の明確な記載
請求書の内訳は、仕事内容や商品ごとに、数量、単価(税抜)、金額を詳細に記載します。内訳の記載後、最後に消費税額と税込合計金額を記載して、請求金額を明確にしましょう。
軽減税率対応
軽減税率制度に対応するため、10%対象品目と8%対象品目の小計を分けて記載する必要があります。それぞれの税率ごとの消費税額も明記しましょう。
例えば、「10%対象:50,000円(消費税5,000円)」「8%対象:30,000円(消費税2,400円)」のように記載します。
インボイス制度に対応した消費税管理をしよう
インボイス制度の導入により、フリーランスの消費税に関する対応は複雑化しました。特に適格請求書発行事業者となった場合、消費税の計算方法や請求書の記載事項など、考慮すべき点が増加しています。原則課税方式、簡易課税方式、2割特例など、適切な計算方法を選択し、適格請求書の必須記載事項を遵守することが重要です。
事務負担は増えますが、正確な対応により取引の透明性が高まり、ビジネスの信頼性向上にもつながります。消費税に関する知識を深め、適切に対応していきましょう。
「PE-BANK」は、フリーランスエンジニアをサポートするエージェントです。フリーランスのエンジニアが、本来の仕事に注力できるよう、案件の提案から事務作業まで一括して請け負うことを特徴としています。フリーランスとして働くことに興味があるエンジニアの方は、ぜひPE-BANKにご相談ください。
この記事をシェア
関連記事