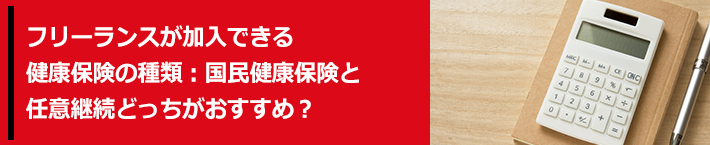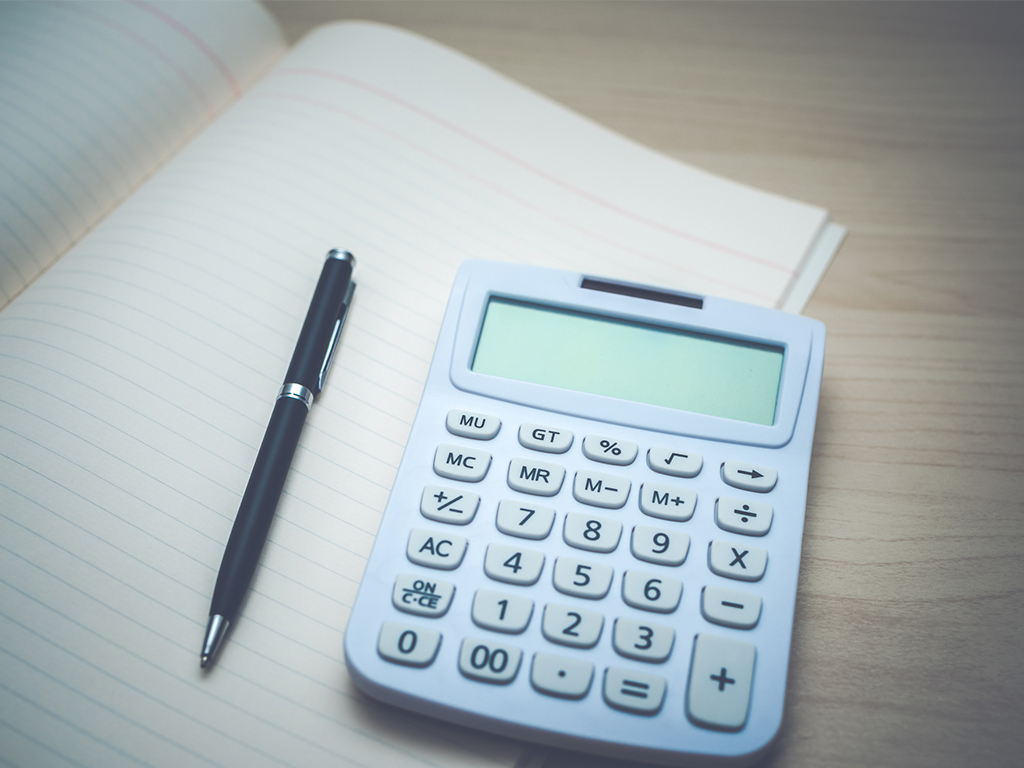更新日:
今回のテーマは「フリーランスになるあなたにとって、国民健康保険と任意継続保険のどちらが得か」です。
会社員からフリーランスの個人事業主に変わる際に、多くの方が悩むのが「どの保険に入るべきか」という問題。ここでは任意継続保険と国民健康保険のメリットとデメリット、それからあなたにとっておすすめはどちらかについてご説明します。ぜひ参考にして、あとで後悔しない選択ができるようにしておきましょう。
![]()
フリーランスが加入できる社会保険は3つ
会社員からフリーランスになった際に選べる保険は以下の3種類。まずこれらの選択肢についてしっかり理解しておきましょう。
フリーランスの保険その1――国民健康保険
国民健康保険は、フリーランスなどの企業勤めをしていない人が加入する健康保険です。保険料は前年度の所得によって計算されます。そのため、サラリーマンから独立した人や、昨年の所得が多かった人は保険料が高額となってしまう特徴があります。
フリーランスの保険その2――任意継続保険制度
任意継続保険とは、勤めていた会社の社会保険や健康保険を退職後もそのまま継続する方法のことです。退職時に契約を延長するように申し出れば可能です。退職日までに2ヶ月以上継続して社会保険に加入していた人が条件です。
ただし、任意継続ができるのは2年間のみ。また、会社と折半していた保険料が退職後は全額を負担することになるので、原則は倍の保険料になります。ただし上限があるので注意が必要です。
フリーランスの保険その3――健康保険の被扶養家族として加入
これは家族の健康保険に被扶養家族として入ることです。子供の頃はそうなっていたはずなので、覚えている人もいるのではないでしょうか。この場合はあなたの保険料の負担は実質ゼロですが、扶養に入れる基準は厳しいため、あまり現実的とは言えません。
・被保険者と3親等以内であること
・あなたの年収が130万円未満なおかつ被保険者の年収の1/2未満であること
・被保険者と生計を共にしていなければいけない
・退職日の翌日から5日以内に加入しなければいけない

任意継続保険と国民健康保険のメリットとデメリットを考えてみる
もし、被扶養家族になれる条件が揃っているなら、金銭面の負担的に、健康保険の被扶養家族として加入するのが一番いいでしょう。しかし条件が厳しいので、結果的に「任意継続保険」もしくは「国民健康保険」という二択に絞られることがほとんどです。
結論から言えば、任意継続保険の方がお得である可能性は高いですが、念のためそれぞれのメリットとデメリットを見ていきましょう。
国民健康保険のメリットとデメリット
国民健康保険のメリットは、所得が基準値を下回った場合は、自動的に減額してもらえることです。デメリットは所得が上がれば保険料も割高になること、それから扶養家族がいる場合はその分保険料が高くなる点です。
任意継続保険のメリットとデメリット
任意継続保険のメリットは、まず所得によって保険料が変わらないので将来の見通しが立ちやすいということ。つまり独立した1年目の収入が会社員時代よりも多くなるならば任意継続にしておいた方が安くなる可能性が高いと言えます。また、扶養家族も保険対象に含まれるメリットもあります。扶養家族が多い場合はお得になります。
デメリットは会社員時代のおよそ倍の保険料になること。会社と折半できなくなるためですが、上限があるのでしっかり確認をして負担額を見極める必要があります。

任意継続がおすすめの人はどのような人か
国民健康保険は誰でも加入できますが、任意継続保険は加入に色々制限があります。
そこで任意継続におすすめな人はどのような人か、ということを押さえておくことが合理的です。もしここに該当しなければ国民健康保険にしましょう。
任意継続がおすすめの人その1――扶養家族が多い人
任意継続は扶養家族の人も保険の対象に含まれるので、扶養家族が多ければ多いほどお得です。逆に、一人暮らしの方や、独身の方の場合は国民健康保険の方が良いでしょう。
任意継続がおすすめの人その2――独立して収入が上がる可能性が高い人
国民健康保険は所得に応じて保険料が変わるので、収入が上がる場合は任意継続の方がお得である可能性が高まります。健康保険の保険料は最高でも月額28万円の水準で計算されるため、それ以上稼いでいる人は、任意継続の方が得になります。またサラリーマン時代に月額56万円以上の水準給与を得ていた方は、上限に達して倍の保険料とはならないため、任意継続の方がお得です。
まとめ
以上、会社員からフリーランスに変わったエンジニアの方のために、国民健康保険か任意継続、どちらにすべきか、そしてそのメリットやデメリット、おすすめの人についてご説明してきました。
月額の報酬によってどちらが良いかということが決まるのと、扶養家族がどれくらいいるかということによって選択肢が変わってきます。収入の基準は56万円。扶養家族がたくさんいる人、それ以上稼げている人は任意継続の方がお得になる可能性が高いです。